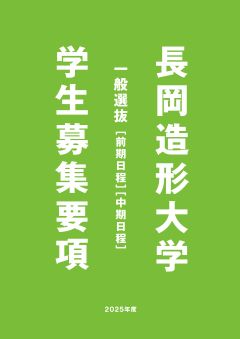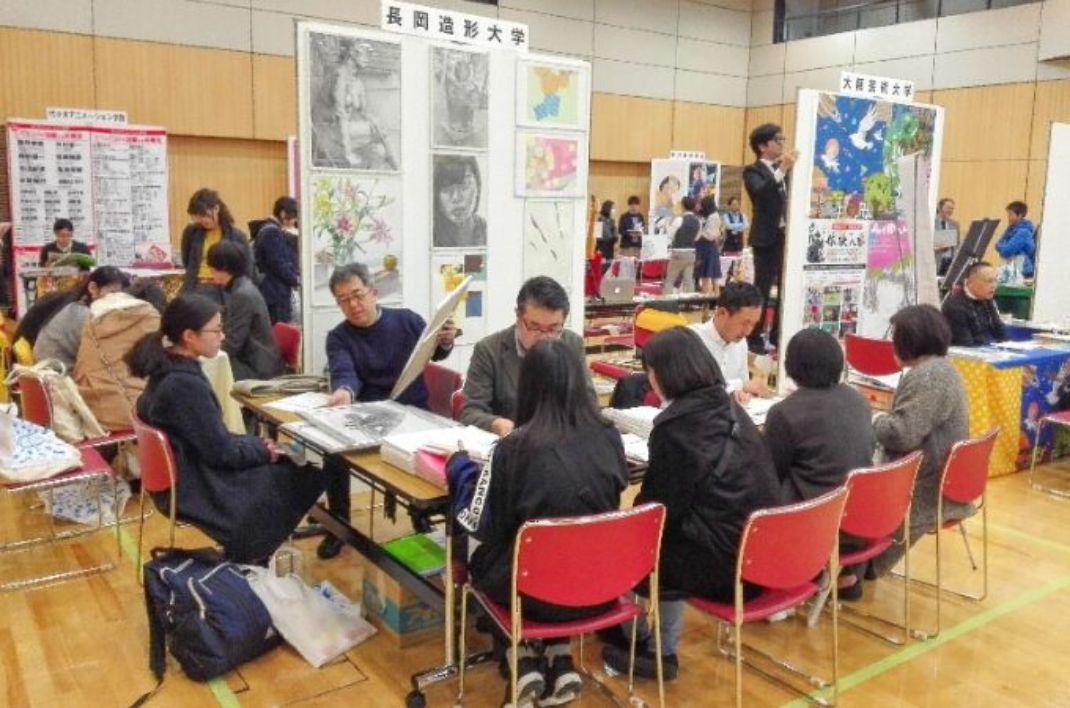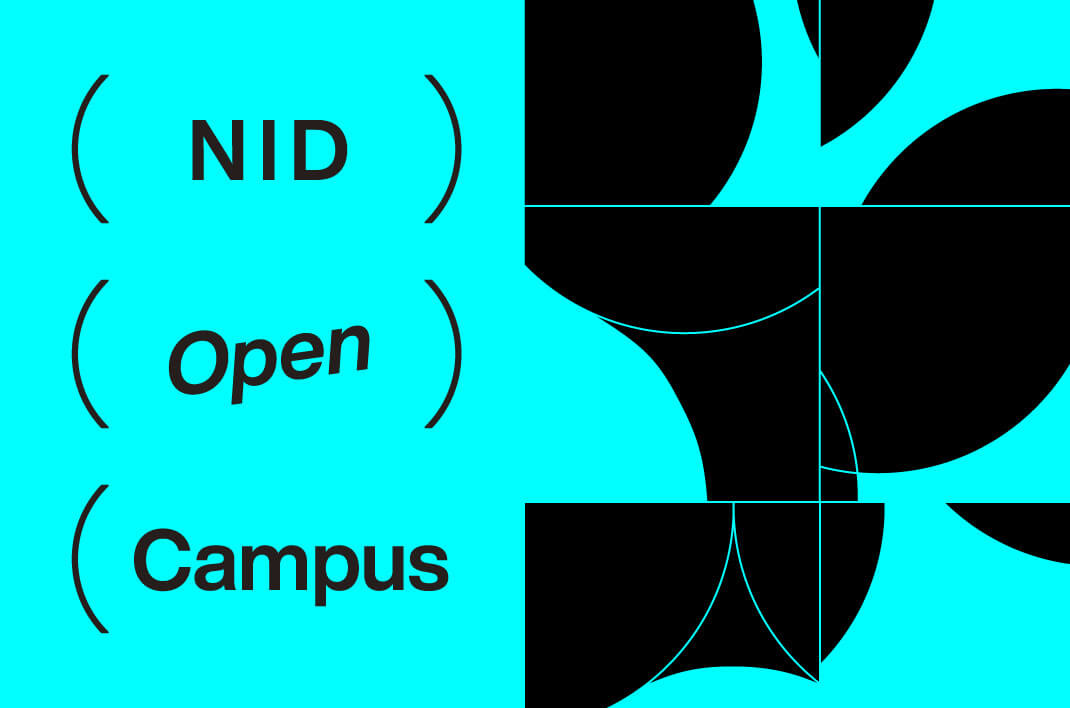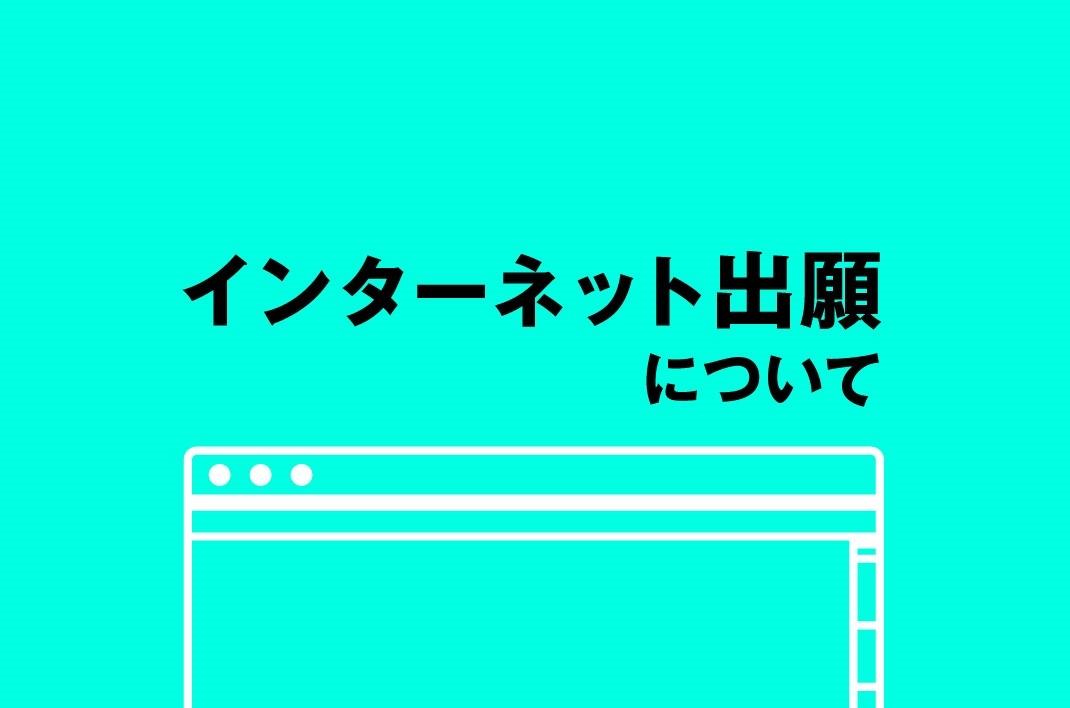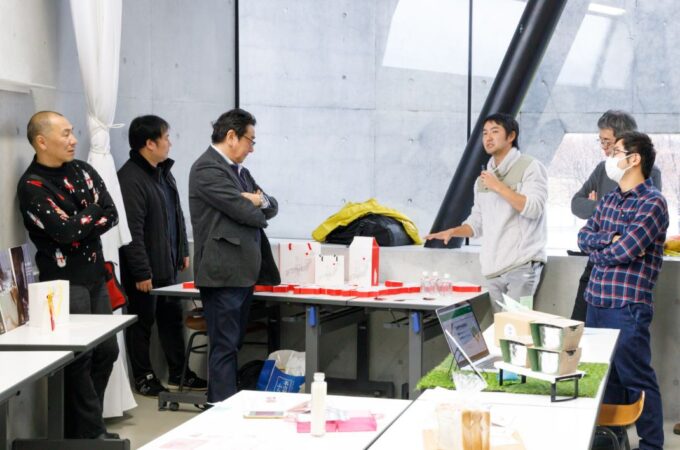教育情報の公表 教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報の公表について
目次
教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、以下のとおり本学の情報を公表するもの。
(令和6年4月1日公開)
1. 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(第22条の6第1号関係)
本学教職課程においては、美術・工芸とデザインに関する知識・技能・思考力・表現力、及びデザインマインドをあわせ持った中学校・高等学校美術科教員の養成を目的とする。
教職課程の教科に関する科目としては、1年次において、総合的な基礎造形教育科目による「基礎造形実習Ⅰ・Ⅱ」を前期・後期に設けている。2年次以降の「美術・工芸基礎演習」とあわせて、絵画(描写)・彫刻(造形)・工芸(素形材)・デザインの専門基礎力を身につける。このほか、1年から3年次にかけて、「美術論」、「西洋美術史」、「美術解剖学」などの理論的な必修科目を学ぶ。
これらにより、基礎造形実習の実践的活動と講義系の理論学習の相互関係による分野を越えた造形要素の共通認識及び技能修得が可能となる。これは、本学における造形教育の根幹的役割を構成するものである。
教科の指導法に関する科目としては、3年次の「美術科指導法」において学校教育現場で通用する美術科の実践的指導力を身につける。
教育の基礎的理解に関する科目としては、2・3年次に「教職入門」、「教育原理」、「教育制度論」などを履修して、教師をめぐる問題、教育の歴史、生徒の心理学的理解、教育法制、教育課程の理論などに関する知識・技能・思考力・判断力を身につける。
道徳、総合的な学習の時間、特別活動等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目としては、「道徳指導法」、「教育方法・技術」、「総合的な学習の時間及び特別活動指導法」などの科目を履修して、理論的な能力ととともに実践的な指導力を身につける。
さらに「特別支援教育」の内容として、学校における介護等体験実習を実施する。
教育実践に関する科目としては、4年生に対して、教育実習関係科目である「事前・事後指導」、「教育実習Ⅰ・Ⅱ」がある。介護等体験を含めて、3年次までの学びを通して、中学校・高等学校において数週間の教育実習を適切に行える能力が身についていると考えるが、学生一人ひとりの個性に応じた親身の指導を行う。「教職実践演習」では、教職課程の最終段階のまとめを実践的に行う。学校現場にも改めて出向いて行き、教員・生徒と関わるなかで、自らの教職課程の学びを振り返り、今後につなげる機会とする。
このほか、視覚・プロダクトデザイン系演習・実習、コンピュータ系CAD実習、3DCG実習に及ぶ広範囲の授業が履修可能となっている。このことは従来の専門分野ごとの授業構成のみではなく、造形表現を広い視点から考察し、社会と人間に積極的な働きかけを行うことにより、社会変革を可能としていく資質・能力の育成をも目指すものである。このように様々なデザイン分野の授業をも履修することにより、教育職就職後に主体的に実践・活動できる資質・能力を育成する。
3年次からは志望した各コース及び専門領域において、制作活動を行う。このことにより、美術・工芸に関する専門家としての自信を持って、様々な教育場面に対応できる能力が身につくと考える。
2. 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること(第22条の6第2号関係)
3. 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること(第22条の6第3号関係)
4. 卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること(第22条の6第4号関係)
免許状の種類および取得件数(過去5年間)
| 免許状の種類/ 取得年度 |
令和 元年度 |
令和 2年度 |
令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中学校教諭 一種免許状(美術) |
10 | 12 | 13 | 13 | 8 |
| 高等学校教諭 一種免許状(美術) |
10 | 12 | 13 | 13 | 8 |
| 高等学校教諭 一種免許状(工芸)※ |
10 | 12 | 13 | – | – |
※高等学校教諭一種免許状(工芸)については、平成30年度以前入学者のみ取得可能
5. 卒業者の教員への就職の状況に関すること(第22条の6第5号関係)
| 卒業年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教諭 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 講師 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
令和6年3月現在
6. 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること(第22条の6第6号関係)
教職課程を履修する学生の対応や相談を受け付ける窓口を設定し、一人ひとりきめ細かい履修指導を行う。教職課程の運営については、教職に係わる科目を担当する専任教員を中心に行うが、必要に応じて教務部長、美術・工芸学科長が意見を取り入れ、教職運営協議会や全学組織である教務委員会において検討する。
マイリストに追加する